9月12日の明神ヶ岳山頂に達した時点で不本意な終わり方をした「箱根大涌谷のいま その2」の続きです。ただこの記事を「その3」にしてしまうと、肝心の箱根山で何が起こっているのかを示すのがどうも「その4」になってしまうな勢い(最近別の論文を読み始めた)なので、今回「その2・5【番外編】」としてお送りします。この記事では大涌谷の写真は一切ありません。しかしあくまで続きです。
なお本文中の噴火年代や噴出時期について「○万年前」とあるのは目安の数字です。できる限り出典を明示していますが、数字は論文の執筆者や年代測定法などによって多少の違いがあることをご了承ください。
 チラリと相模湾
チラリと相模湾15:00に明神ヶ岳山頂を出発すると、まもなく左手に相模湾が見えました。特徴のある高架の道路なので、西湘バイパスの早川 JCTであるのは一目瞭然です。雲さえなければ、三浦半島なら余裕で見わたせそうですね(箱根ハイキングコース : 明神ヶ岳ハイキング)。

真鶴方面は雲が出ていたので見通せませんでしたが、外輪山の尾根の手前にある、二子山からこちら側に延びる低い尾根は鷹巣山や浅間山だと分かります。箱ペディアによりますと、
湯本より湯坂山・浅間山・鷹之巣山など箱根新期外輪山の峰々を通り、芦之湯へ下り、精進ヶ池の淵を経て箱根権現に向かい、それより芦ノ湖畔の芦川宿から箱根峠を経て三島に至る道を湯坂路という。
この道がいつ開かれた道か定かではないが、「日本紀略」によると延暦二十一年(八〇二)富士山が噴火し、その焼砕石で足柄路が塞がれたので、その代わりに「筥荷途」を開いたとある。あるいはこの道が後に湯坂路と呼ばれるようになったのかもしれない。―昭和61年発行『箱根温泉史』
西暦 800-802 年の富士山の延暦噴火で足柄路が通行できなくなったため、これらの山の尾根を巡って、二子山の手前の芦之湯に下りる代替街道がつくられたそうです。結局1年で足柄路が復旧したため「筥荷途」は廃止されたのですが、鎌倉時代には湯本と芦之湯が湯治場として知られていたという話もあります。
 最後の大涌谷ショット
最後の大涌谷ショット 大涌谷北側新噴気(E領域)
大涌谷北側新噴気(E領域)さて中腹の登山道の見晴らしが悪いため、上からのぞき込む大涌谷ともここでお別れです。気温が下がってきたせいか、大涌谷北側斜面の新噴気域が一面白い煙(水蒸気)で覆われはじめました。
 最乗寺への分岐
最乗寺への分岐なだらかな道を下りてゆくと、数分で最乗寺(南足柄市)への分岐にたどり着きました。
 歩道管理ナンバー
歩道管理ナンバーさて外輪山ハイキングで重要なことをひとつ。金時山入口の登山道を入ったところでも見かけたのですが、ハイキングコースには箱根町管理の「歩道管理ナンバー」が 50m 毎に設置(ないところは数字が抜けています)されていて、GPS が使えなくてもどれくらい歩いたかが分かるようになっていてありがたかったです。

15時30分に明星ヶ岳登山道と宮城野に下る道との分岐である鞍部に到着しました。


さてここから下りの15分間はコース最大の難所。登山道を整備するのも難しいらしくやや乱れていますし、明星ヶ岳溶岩の巨石が随所にあって通行方法を考えてしまう箇所もありました。今回下りなので必要ありませんでしたが、ロープを使わせて巨石を登らせるところも1か所あります。
 宮城野別荘地間近(15時53分)
宮城野別荘地間近(15時53分)でも足場材でできた手すりのある階段が見えてきたら、宮城野はすぐ近くです。
しかしうっかりハイキングコースを間違えて、舗装された明神平別荘地内に迷い込んでしまったのが16時ちょうど。
 スマートフォンの表示
スマートフォンの表示別荘地内の道路って曲がりくねっているのでハイキングコースでないのにはすぐ気付きましたが、Android スマートフォンの Google Map によると、登山道が県道723号線に化けて表示されるのです。しかも描かれているのは太くて立派な線。センターラインのある道路かと錯覚してしまいそうですが、車が通れる道は別荘地を外れてはどこにも見当たらないし県道の標識なぞどこにもない有り様で、疲れきった状態では判断を誤ります。
 「明神ヶ岳近道」
「明神ヶ岳近道」そういえば別荘地をずいぶん下ってから、登山道の案内とは思えない「明神ヶ岳近道↑」という標識を見つけたなぁ。あれがもしかしてもしかすると県道だったのか?!
そこでこの記事を書きながら Google 先生にお伺いをたててみると、「隠れ盲腸険道 神奈川県道723号関本小涌谷線宮城野狭隘区間(1) - フィールドは果てしなく - 」というブログでまさにあの階段が県道だったことを知りました。
 Yahoo 地図も県道に
Yahoo 地図も県道にしかも今の Yahoo 地図では Google Map 同様、別荘地わきの登山道が県道723号線に昇格しているのです(ホントかよ)。
残念ながら僕が別荘地に迷い込むまでに通ってきた登山道は県道でないのですが、なるほど県道かどうか判断に迷う時は、道路境界を示す杭やカーブミラーの「○○県」のステッカーを探せばいいのか。勉強になりました。
# 日本武尊伝説の古街道に興味がないと書いておきながら、車も通れない県道の盲腸線にひたすら食いつく自分(笑)
 勘太郎の湯
勘太郎の湯別荘地内をたらいまわしにされたおかげで、身も心もヨレヨレで宮城野にある温泉施設「勘太郎の湯」にたどり着いたのは16時50分頃。温泉で生き返った後バスでちょっと遠回りをして、箱根登山鉄道とケーブルカーを乗り継いで宿に着いたのは19時でした。
# 18時を過ぎると途端にバスの本数が少なくなるのね>強羅付近
 雨のユネッサン
雨のユネッサンそして一夜が明けた日曜日の朝、箱根は小雨~にわか雨でした。仄かに硫化水素の臭いが漂う雨の中を歩きたくなって9時前にチェックアウトして小涌園バス停まで歩きました。
 小涌谷駅
小涌谷駅そして箱根登山鉄道箱根湯本行に乗りました。向かう先は小田原市神奈川県立生命の星・地球博物館。

小田急に乗り継ぐのに遅れて、箱根の玄関口に位置する地球博物館に着いたのは10時半。案内所でエントランスホールの「特別パネル展示」だけを見に来たと告げると無料でどうぞと。
 「箱根火山の今を理解する」の特別パネル展示
「箱根火山の今を理解する」の特別パネル展示9月第一日曜日に開かれた一般向けの講演会「箱根火山の今を理解する」の特別パネル展示(最終日)が13日まであったのです。これらのパネルについて、詳しくは「その3」で。
地球博物館に生物や地学に関する本や化石の販売コーナーがあったので、「かながわの自然図鑑①岩石・鉱物・地層」を購入して、博物館の裏手にある温泉地学研究所に着いたのが11時15分でした。
 おんちけん
おんちけん
ここは神奈川県立のお役所なので、開所時間は平日8時半~17時になっています。箱根に限らず神奈川県内の温泉について調査しているところなので、1階には展示コーナーもあります。
 溶岩鍾乳石
溶岩鍾乳石休日にやって来た僕のためにか、玄関に面白いものが飾ってありました。真鶴町産の溶岩鍾乳石です。


「ひだ状の構造は、石灰岩地帯の鍾乳石と似た形をしていて、たいへん珍しい溶岩です。溶岩流の先端部で内部から高温の溶岩が膜状に滲み出したものと思われます。
真鶴町の北部で切り出される石は、真鶴石または根府川石(銘柄名 小松石、本小松石、新小松石)と呼ばれ、庭石や墓石としてよく利用されています。 安山岩(真鶴町岩字天辺)」

博物館でいただいた「箱根ジオパークガイド2」によると、真鶴町の採石の歴史は奈良時代に始まっていて、鎌倉時代に入ってから長谷大仏の礎石や北条一族の墓石など広く用いられるようになって、海辺という立地から各地の城の建築資材(江戸城の石垣の9割は真鶴産だとも)として石材業が発展したそうです。真鶴町の地形は20万年前から13万年前とされる箱根外輪山の噴火による溶岩流「本小松溶岩」や「真鶴溶岩」でできていますからね(箱根火山外輪山噴出物の全岩主化学組成,2007)。どんなに切り出しても石には困らない所です。
 箱根湯本駅
箱根湯本駅温泉地学研究所を出て箱根湯本駅へ戻ったのは12時前。箱根新道や旧東海道が通る須雲川沿いの貫入を見て帰るか、秘境・堂ヶ島渓谷に行くか悩みましたが、ここは秘境を選択。
しかも箱根登山鉄道で運転台側の座席が空いていたので、鉄分の多い自分にはスイッチバック撮影のチャンスにしか見えません。

箱根登山鉄道のスイッチバック(2015年9月13日撮影)
満席の車内に響くインターナショナルなおしゃべりがにぎやかで、路線案内がほとんど聞こえませんが(汗)

ちなみに箱根湯本行上り列車で「出山信号場」に停車すると、眼下に鉄橋をわたる強羅行下り列車が見えることもあります。箱根湯本行が「上り列車」なのはややこしいですけどね。


12時18分観光客でごった返す宮ノ下駅下車。駅を出たら急坂を下りて国道1号線に出ます。

まだ道路も鉄道もなかった明治時代初期、箱根に宿泊する外国人客は「籐椅子の下に竹棒を付けた四人の人夫が担ぐ「チェアー」と呼ばれる山駕籠」に乗ってやってきたそうです(箱ペディア【塔之沢―宮ノ下間の道路開削】)。富士屋ホテルが開業したのは明治11年と言いますから、宮ノ下まで人力車道路が開通する明治20年まで、日本初のリゾートホテルは鎌倉時代とほとんど変わらない交通事情の山奥にあったわけです。
さてふつうの観光客は宮ノ下にある老舗旅館やアンティークショップに行くのでしょうが、僕のお目当てはさらに古い時代の箱根を見に行くことです。駅を出て5分。国道1号を富士屋ホテルの方へ向かう途中にある郵便局の先に、エクシブ箱根離宮の手前に下りる道があります。そしてしばらくイロハ階段を下りて、今は工事用の衝立で覆われている「ホテル大和館」「対星館 花かじか」(堂ヶ島温泉)の空き地にできた迷路を過ぎて10分でこんな景色に。


早川沿いの堂ヶ島渓谷です。夢窓橋を渡って右に曲がれば「夢窓国師山居の跡」(白糸の滝には行けません)、左に曲がればお手軽なトレッキングコースの始まりです。
 早川凝灰角礫岩
早川凝灰角礫岩早川と蛇骨川ではさまれた富士屋ホテルのある宮ノ下の台地は、今はなき成層火山「先神山」が4万1000年前に崩壊してから流れ出た早川泥流でつくられた岩石(早川泥流堆積岩、CC2)が、川の浸食で削られて残った土地。そういう台地が早川沿いの大平台や塔ノ沢、箱根湯本に点在しています。では早川に削られた渓谷の一番下に見える岩盤はいつできたかというと、箱根火山ができる前の時代(博物館で買った「岩石・鉱物・地層」によれば420万年前)のもので「早川凝灰角礫岩」と呼びます。
 図10(a)早川沿いの段丘分布と河川縦断図
図10(a)早川沿いの段丘分布と河川縦断図 図10(b)段丘を横断する地形・地質断面図
図10(b)段丘を横断する地形・地質断面図【出典】箱根火山中央火口丘群の噴火史とカルデラ内の地形発達史(2008)より


ただもっと渓谷を眺めたいと思っても、チェンバレンの小路(堂ヶ島渓谷遊歩道)を進むと渓流から離れていきます。しかも足元をよくみるとカワザトウムシが蜘蛛の子を散らす様に走っています。目立たない生き物ですが動きが俊敏で気配を感じるとあっという間に見えなくなってしまいます。なので踏みつけたかもという心配はしなくてもよいでしょう。



小路を進むと、手の込んだつくりの沢もありますが、その先にある塔ノ沢水力発電所の1号開渠を過ぎると一面ぬかるみなので注意。


この辺一帯は箱根の電力を支える東京電力の敷地で、水力発電所(流れ込み式)や変電施設群があります。塔ノ沢水力発電所は明治42年7月、川久保水力発電所は昭和28年7月運転開始です。
Find Travel の記事では、川久保水力発電所の前身は明治39年に富士屋ホテルが設置した「宮ノ下水力発電所」のようです。
さて発電所の対岸の、早川に蛇骨川が流れ込む付近で「早川泥流堆積物(CC2)」を見つけることができました。

 早川泥流堆積物(CC2)
早川泥流堆積物(CC2)箱根火山中央火口丘群の噴火史とカルデラ内の地形発達史
a)早川泥流堆積物(CC2; 41ka)
早川泥流堆積物(CC2;火山円礫岩; Kuno, 1950)は、シルトや細砂を基質として安山岩の円~亜円礫が混在する泥流堆積物である。
箱根町大平台(Loc.86)や宮ノ下などの早川沿いに分布する河成段丘を構成する。箱根町木賀では、よくしまった淡黄色シルトを基質として、径2m以上の一部赤色参加した安山岩の亜円礫を含む土石流堆積物として確認できる。
早川泥流堆積物のもととなった「先神山」は箱根のどこ辺にあったかは後に回します。


さて日曜日のお昼だというのに誰にもすれ違わないまま、13時16分遊歩道の終点にある吊り橋に到着しました。
「ハイカーの方へのお願い
この橋は東京電力(株)
の管理用で、好意により
通らせていただいており
ますので、制限を守って
下さい。
箱根町」

東京電力が水力発電所の管理用に設置している吊り橋ですが、渓谷にはなかなかピッタリです。吊り橋を渡って蛇骨川の合流地点の方に目をやると、風景に溶け込んだ塔ノ沢発電所の取水口が見えてきます。

遊歩道の終点は真っ白な民家のガレージ横。そういえば食事を忘れていた…。どこかの風呂屋で食事をと思ったのですが、
 ての湯
ての湯近代化された建物と満車の駐車場で敬遠。
 函嶺
函嶺その向かいにあった「函嶺」に寄ったところ、予約が入っていて 16:00 までお待ちいただきます、と言われて諦めました。


ちなみにこの洋館は元病院。碑文には東京の刀剣商小松崎茂寿翁が底倉温泉に滞在中病気にかかったことをきっかけに、医師を呼びよせて「函嶺医院」を開業させたことが書いてあるという(箱根底倉温泉・函嶺(神奈川県足柄下郡箱根町底倉) ~旧函嶺医院)。明治17年というとまだ塔ノ沢までしか人力車道路が開通していなかった時代。
洋館の使い道がなくなり風呂屋になったのは平成11年からという話ですが、いつまで続けられるのでしょう。近いうちにまた寄ってみたいものです。

蛇骨川にかかる国道138号線「八千代橋」から先ほど回った東京電力の変電所が見えますね。変電所から伸びた高圧線は、標高500メートル付近を通っている鉄塔に接続されています。頂上は明星ヶ岳かな。


八千代橋を渡って右折すると、蛇骨渓谷を上から眺められる太閤石風呂通りと名付けられた遊歩道に。地図をみても滝記号はないのですが、ての湯の裏山のあちらこちらから水が染み出しています。これもまた早川泥流堆積物なのだろうな。
 そこくらの湯つたや
そこくらの湯つたや遊歩道を入ってすぐに「そこくらの湯つたや」さんを発見。手作りの看板に民家のような構えなので、恐る恐る入っていくと自動販売機据付の裏口が開いていた。靴をぬいで直角の通路を曲がった先に番台があって、二千円札を出したら、「今時こんな札を使う奴がいるとは」なんて言われた。しかも旅の記念に名入りタオルがあるか聞いたら「入口の看板を見ていないのか、うちはレンタルしかない」と。すこぶる感じの悪い風呂屋だったが、


内湯のみ洗い場があり、露天風呂に行くには一旦服を着る必要があったが、たまたま誰もおらず貸切状態で最高だった。きっと愛想悪くすることで、お客を選んでいるのだろう。

風呂だけコースで利用できるカウンター席(飲食物持込不可)から渓谷が眺められたのもよかったです。ただ番台の旦那さんに何か注文するのは気が引けたので、自販機で飲料を買って今後の行き先を決めることにしようと廊下に出たら、面白いパネルが展示されていました。
江戸時代後期の文化8年(1811年)に、分窓・弄花と名乗る二人組が当時の箱根温泉の様子を10巻10軸の絵巻物にまとめたもの、『七湯の枝折』(箱根町重要文化財、箱根町立郷土資料館所蔵)。その一部を写真パネルにしたものが、元の所有者である「つたや」でも公開されているそうです。その一部をここでご紹介。

湯本
天平10年(738年)に加賀白山の僧侶が疱瘡に苦しむ人のために、温泉を沸き出だせたという言い伝えがある。江戸時代に入ると、お伊勢参りや富士山に行く団体客が、旅の途中で立ち寄っていくようになり、現在の「日帰り温泉」のような賑わいをみせていたという。

塔之澤
塔之澤は江戸時代に発見された新しい温泉場ですが、熊野の神様のお告げによるとか阿弥陀時の弾誓上人が沢すじを鉄の杖でつつきわきださせたという諸説があるという。また水戸光圀が明の学者朱舜水を伴って訪れたとき、舜水が「明の温泉場り山より素晴らしいので、勝り山と名付けた」という話も。


堂ヶ島
宮ノ下から早川の渓谷に向かって、曲がりくねった急坂を下りたところにある温泉場で、早川が迂回して流れるので島のように見えることから、その名がついたとされています。
貞享4年(1687年)熊野権現のお告げで掘り出されたという言い伝えがあり、大滝・小滝という温泉は腰痛やできもの、婦人病によく効くと知られていました。穴の湯は現在のサウナに近いものだったらしい。

宮ノ下
宮ノ下は箱根山の中腹に開けたところで、40軒ほど家があり、弓を射る遊技場やソバ屋など便利な所でした。りっぱな構えの湯宿が多かったため、塔之澤とともに江戸の大名たちに愛されていました。大名を迎えるときは玄関に幕を張り、門前に「○○様お泊」という関札を掲げる習慣がありました。家々には樋をかけて温泉を引いていたため、中には打たせ湯にしていたところもあったという。
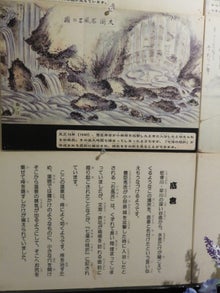
底倉
蛇骨川・早川の深い谷底から水音だけが聞こえてくることから底倉と名付けたという言い伝えがあります。豊臣秀吉が小田原城を攻撃したときに入浴した岩風呂は長い間埋まっていましたが、分窓・弄花が訪れる直前に掘り起こされました。痔に効くとして、湯宿では腰掛に小さな穴をあけて、お尻の穴に温泉の蒸気をあてる仕掛けも備えられていました。
 画像がブレているのは察してください(笑)
画像がブレているのは察してください(笑)木賀
鎌倉時代、源頼朝の家臣木賀善司吉成は重病にかかりもう助からないと思われたとき、一人の老僧が「わたしについてくるように」と告げ、当地で呪文を唱えて湯をわきださせ、善司に2週間入浴したところ病気がすっかり快復したという言い伝えがある。上湯・大滝湯・菖蒲湯・岩湯と呼ばれる温泉があり、中でも上湯から江戸城に温泉を献上したこともあるという。
芦之湯
箱根山の山上にあり、避暑地の温泉場として七湯の中で当時一番にぎわっていたのが芦之湯。宿には内湯がなく、泊り客は温泉場中ほどの「惣湯」に集まり入浴していました。またここには酒屋やソバ屋、野菜や魚を売る店、床屋、呉服屋までありました。また町はずれにあった「達磨湯」は眼病に効くと評判になり、温泉をいれて自宅に持ち帰る人のために小さな竹筒を作る商売のお店もありました。
15時前に「つたや」を出て、太閤岩風呂を観に行きました。


1590年の豊臣秀吉が小田原城攻略のため、近くの石垣山に4万人の人員を投入して80日間で総石垣の城を築いている間、将兵を癒すために底倉の地に石風呂を作ったのが「太閤石風呂」の始まり。そして5月18日に伊達政宗の帰順を祝うために、徳川家康や淀君をはじめ多くの武将を引き連れてこの地で盛大な宴を催したという記録があります。
なお「七湯の枝折」によると、「太閤石風呂」向かいの河川敷に『細長い自然石の中より熱湯が湧き出ている所があり、大蛇の入りし湯「大蛇の湯」がある』と書かれているそうですが、現在正確な場所は不明だそうです。とはいえこの付近で高温の源泉を集湯していることから、源泉集湯場付近ではないかと考えられるとのこと。でも「源泉集湯場」自体がどこにあるかよそ者に分からないし、渓谷の河川敷にすら近づけないので、「湯煙立つ20メートルの名瀑『太閤の滝』を散策してくれ」と看板に書かれても、上から滝なんか見ても面白くもないし。
もうバス乗って帰ろうと思ったのが 15時過ぎ。しかし上底倉バス停で待てど暮らせど宮ノ下行の箱根登山バスが来ない(伊豆箱根バスは2本通過したのに)。仕方ないので堂ヶ島渓谷遊歩道の出口近くにある「木賀温泉入口」まで歩いて、桃源台駅行に乗り、海賊船で箱根町港へ。
そそこの記事の最後に、早川泥流堆積物のもととなった「先神山」は箱根のどの辺にあったかを書いておきたいと思います。
箱根火山の最近5万年間のテフラ層序と噴火史(1999年8月)には
平田(1991)の化学分析結果は,Hk-Tpnの噴出で軽石流噴出期が終了し,pre-Kamiyama噴出によって中央火口丘期活動が始まったとする本研究の解釈を支持してい る。噴火年代は,Loc.113におけるpre-Kamiyamaの層位から、おおよそ50kaと考えられる。
芦之湯北方には、神山・駒ヶ岳起源の溶岩流に覆われるやや開析の進んだ古い地形面(先神山)を 確認できる(図2)。現在、この地形面は人工改変が進んでおり,被覆層は確認できなかった。図2 箱根火山カルデラ内の地形分類図
 蛇骨川から見える丸山
蛇骨川から見える丸山底倉から小涌谷方面を眺めたときに見える、丸山付近の「箱根湯の花ゴルフ場」がある辺りと考えられているようです。「その3」に続く。
